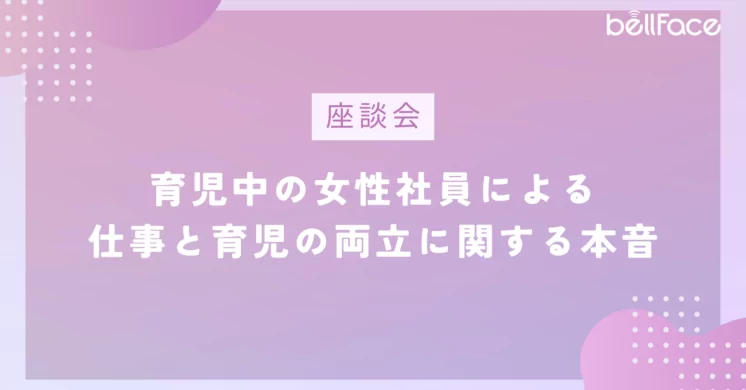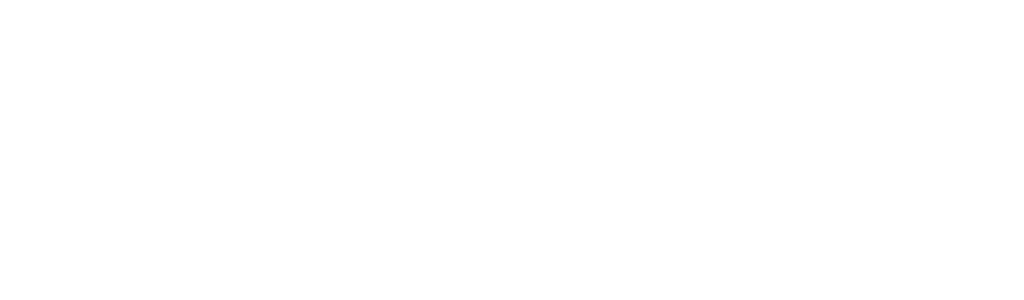目次
2023年2月にプロダクト管掌における取締役が交代したベルフェイス。
近年のプロダクト開発、事業のピボットを牽引してきた山口(以下:ZIGOROu)が退任し、プロダクト組織の執行役員として組織を統率してきた溝口が取締役に就任する形となりました。
今回は、新旧取締役の対談企画として、その交代劇の裏側に迫るインタビューを実施しました。
任せられる組織ができたタイミングでのフェロー就任

ー ZIGOROuさんの退任の背景から教えてください
ZIGOROu:
実は入社したタイミングから、自身がいない状態でも成長をする組織、体制をつくることを想定していたんですよね。なので、この2年間で順次マネジメント層を引き上げていってましたよね。最初はVPoEの杉山さん、次はDoPの溝口さん、といった順番で。
引き上げていくにあたって、実際に経営のアジェンダを横について見てもらったり、経営会議の直後に1on1を通じて会議の振り返りやその時必要なアクションを検討してもらったり。そういうことを1年くらい実施しましたね。
溝口:
そうですね。徐々に経営にも伴走させていってもらった感覚があります。
ZIGOROu:
なのでフェロー就任までの助走期間は用意していたんですが、じゃあ「いつから」という話については、ある程度組織のオペレーションが回る形になるまで、ということを想定していました。
他社の顧問という役割も複数持っていますが、ここが中々うまくできている会社が少ないんですよね。ビジネスとプロダクトの連携が取れていないだとか、フィードバックループすらできていないだとか。もちろんベルフェイスが完璧にできているとは言いませんが、他社の環境と比較してもかなりレベルの高い組織になってきたという感覚があり、一つの区切りが見えたため、今回取締役の役割を移譲しようと決断しました。
また、直近は短中期事業計画を明確に作り上げたタイミングでもあり、その舵取りは必ずしも僕である必要はないよね、という考え方ですね。
溝口:
ZIGOROuさんは今までの経験の中でも、常に後任の体制とか、自身がいなくなった組織でも回る環境づくりみたいなことって意識されてきたんですか?ZIGOROuさんの中にそういう軸があるというか。
ZIGOROu:
特別意識をしていたわけでは無いですが、よく考えてみるとやっていたという感じですね。例えば前職でも、組織長としての役割は引き継げると思い、後任を見つけてから退職を選択していたので。
また、インディビジュアルコントリビューターとしての役割をそのまま引き継ぐことは難しいですが、会社で扱っていたプロダクト類のアーキテクチャを見れる後任の育成ということはずっとやっていましたね。
溝口:
なるほど。結果的に後任も育成しながら働かれてきたという今の話も受けて、僕自身も最初からこうなるということを言われていたわけではないですが、自然と業務を進めていく中で適切な役割を与えてもらい、他のメンバーにも権限委譲が進み、この形になったなと思っています。
ZIGOROu:
それでいくと、「何を引き継ぐか」は常に考えていた気がしますね。溝口さんも見てて感じたと思うんですけど、経営会議のテコ入れはかなり力を入れてましたよね。プロダクトを中心に据えた組織に変えていくという観点において、その時々に経営で決めなければいけないこと、そして決めたことを組織に対してどうエグゼキューションしていくべきか、ということはすごく意識して。
なんだったら経営会議のあとに背景を溝口さんに説明したりだとか、実際にその意図をどういう風に戦術・オペレーションに落とし込んでいくのかとか、そういう話はしょっちゅうしましたね。
溝口:
確かに。その意味でいくと、経営に関することは常に引き継ぎを受けていた状態ですね。
ZIGOROu:
そうそう。なので、昔出した記事でSlackのスタンプ職人みたいな紹介されてましたけど、別にスタンプばっかり作ってたわけじゃないですからね?笑
第三者視点から冷静な意思決定の支援を

ー ZIGOROuさんのフェローとしての関わり方を教えてください
ZIGOROu:
もともと関わっていたプロジェクトに関しては、段々役割は薄くなっていくと思いますが今後も関わり続けます。あとは、一つの重要プロジェクトの立ち上がりまでを見届ける役割と、一部のメンバーのメンタリング的なことをやる想定です。
逆に経営に関与することは、一歩引こうと思っているところですね。フルコミットで入っているのと、外部からやっていくのではどうしても解像度は落ちるので、口出ししないようにするという感じです。基本的には多くの役割をバトンタッチしているので、現場としては違和感がそんなに出ないと思います。
溝口:
個人的にはZIGOROuさんとしっかりリレーションが築けていることで、第三者視点から意見を貰えることは大きいと思っています。自分たちだけでは意思決定が難しい課題だったり、乗り越えるのが困難な課題にあたったときに、冷静にベターな判断を下すことができますし、そのソリューションとしてZIGOROuさんの人脈から外部のリソースをお借りすることもできると思うんですよね。そういった観点でも、外部からサポートしてもらえることが結構あるなと。
ZIGOROu:
そうですね。僕自身は色々な会社に関わらせていただいているので、社長やCTOの壁打ちをすることもあれば、プロダクトの壁打ちをすることもあります。ベルフェイスもその一環にはなりつつも、在籍していた経験から非常に解像度が高い状態で支援することができると思いますね。
真っ先にパートナーとして選んだのは溝口

ー 溝口さんに取締役をお願いした理由を教えてください
ZIGOROu:
自部門で真っ先に取締役辞任を伝えたのが溝口さんなんですよ。そこがスタートラインという感じで。溝口さんは物事が前に進むことを良しとするというか、及第点でも前進を選択できる人で、何より困難を望みにベルフェイスにきたという、一般的にはM気質な人なんです。笑
だからこそ、真っ先にこの後の体制だとか、引き継ぎだとかを一緒に考えるパートナーにふさわしいと思い口火を切りました。
また、組織長という人間って個のこだわりは明確に持っている上で、それ以上にどれだけ組織のために動けるのかという観点がすごく重要なんですよね。
僕もすごい我が強い人間ではあるんですけど、取締役という立場では強引に組織を運営したことってないんですよね。そういったバランス感を備えた人という部分では、溝口さん以外には選択肢がないという状態でした。
溝口:
ZIGOROuさんは僕の良い部分も悪い部分もケイパビリティを含めてわかってくれているので、最初に話を聞いたときも客観的に見て組織を回す上では僕が適任だと思いました。もちろんチャレンジングな部分もありますが、全く適正の無い中でやれと振られたわけでもないので。ただ、その分しっかりやらないとなと感じましたね。
ZIGOROuさんから話を聞いてからは、僕自身の気持ちの整理もつけつつ、この後の体制をどう考えていくべきなのか、誰に何の役割を持ってもらうべきなのかを順番に決めていったイメージです。
ある程度構想を固めてから、それぞれのキーパーソンに期待値を伝えていくというのが、次のステップになりました。
ー なるほど。ZIGOROuさんの役割をキーパーソンに分散させた形ですね
溝口:
これは僕の主観もあるのですが、この短期間でプロダクトドリブンな会社になれたのはZIGOROuさんの存在が大きかったと思っています。それはZIGOROuさんが取締役、CTO、CPOというそれぞれの役割を担い、いわゆる経営・開発・プロダクトという会社によっては対立構造になりがちな立場を、どこかの視点に偏ることなく「会社にとって一番良い意思決定は何か」を調整してくれていたからこそ、このスピード感で変わることができたのだろうなと感じていて。
では、いざ退任されるとなったときに、その役割をまるっと担える人材を置くというのは簡単なことではなく、複数名で分散する必要があるなと判断したんです。ZIGOROuさんみたいなスーパーマンが必要だよねと思っても、そもそもZIGOROuさんみたいな人っていないので。笑
この判断については、入社当初からZIGOROuさんが後任を育ててくれていたお陰で、ある領域における強みを持った人材が出てきたので、専門性の高い人材を各領域に配置することで、後任の体制を考えることができるようになっていました。
一方で、今までZIGOROuさんが一人で担っていたことを複数人に分散することのリスクも考える必要があります。当然、人それぞれ考え方が違うので、場合によってはぶつかることもあるでしょうし、うまく前に進まないということもあると思います。
誰にどういう役割を持たせてバランスを維持するのか、そしてその期待値をしっかりと伝えるということが非常に重要でした。今いるメンバーが、みんなで同じ方向を見て走れるかという観点こそが、僕の一番の役割だとも思っていますね。
ー それぞれのキーパーソンからの反応はどのようなものでしたか?
溝口:
反応はバラバラでしたね。伝えられた人はもちろんすべからくショックを受けた上で、新体制で自身がどんなチャレンジができるのかということを想像して、その上で気持ちの整理がついたメンバーが今も残ってくれたと思います。
ZIGOROu:
受け止め方は様々だったと思うんですけど、それぞれ自分の役割を考え直して、前に進んでくれる人ばかりだったので有り難いと感じましたね。客観的に見てもベルフェイスは組織としてかなり強くなったんじゃないかな。他社のシンボリックな人材が抜けたときと比較しても、かなりスピーディに体制移行が実行できたなと思います。
“顧客に価値を提供できるプロダクト”を会社全体でつくる

ー 今後の組織、プロダクトについて教えてください
溝口:
組織という観点でいくと、会社として短中期事業計画を策定しているので、まずはその達成に向けて新生プロダクトグループ全員でやりきることが目標ですね。そのためには適材適所で「選択と集中」をしていく必要があると思っています。
全部をやる、ではなく費用対効果の高い領域を選択し、その選択をするために一定のリスクを取っていかなければなりません。この短中期事業計画の達成のために、さまざまな判断が求められてくると思いますが、時にはZIGOROuさんも相談しつつ、組織として明確な意思決定ができるようにしていこうと思います。
また、プロダクトという観点でいくと、短期的な目線では商談機能をリニューアルするという大きなプロジェクトが動いているので、新CPOの岩本さんを中心にやりぬくことが求められています。また、もちろんリニューアルプロジェクト以外でも既存機能のエンハンスによるMRRへの貢献という目線もあるので、既存機能・エンハンスに関わっている人たち含め全員でスコープを達成することが大事です。
併せて、中長期的な目線でプロダクトの価値をどういう方向性で進化させていくのか、別軸で考えていく必要がありますね。リニューアルプロジェクトのプロダクトストラテジーフェーズにおいて、ある程度プロダクト全体の方向性は見えてきているので、そこに向けて調整していく想定です。
ー 会社全体を見た場合はいかがでしょうか?
溝口:
直近のベルフェイスは、プロダクトとセールスの連携が非常に良い状態にあると思っています。単純に仲が良いという話ではなく、健全な議論と落とし所の探り合いができる組織になっているということですね。
例えば、ある方向性でプロダクトを進化させようといった話がでた場合、セールスの観点からSAM/TAMの広がりがあるのかを建設的に議論し、じゃあどこから拡げていくとMRRに繋がるのかといった話ができる組織になっています。
こういった議論を積み上げていきながら中長期のプロダクトの方向性を固めていくと、短中期の計画と中長期の計画がしっかり延長線上につながっていくと思っていて、セールスが売上を作れて、CSがサクセスを生み出し、チャーンされないプロダクトが会社全体で生まれていくと考えています。
もともとはZIGOROuさんを中心に出来上がったこの一体感を崩すこと無く、それぞれの役割で同じ方向を向き、きちんと顧客へ価値を提供し、その対価として健全に売上が立つということが大事だと思いますね。そういうプロダクトを今のメンバー全員で作り上げていきたいです。
ー ありがとうございます。ZIGOROuさんから見て期待していることはありますか?
ZIGOROu:
溝口さんのおっしゃる通りだなと思います。ただ、経営とか組織運営って、動かせる変数って限定的だし、その変数を動かしたからといって必ずしもコトの整理がうまく進むわけじゃないんですよね。だから、人事を尽くして天命を待つみたいな感じで、現実的に動かせそうなところを一歩一歩変えていくしかない。
その一歩として、オペレーションの可視化や、その意義をちゃんと明確にさせること、そしてそれを徹底してトラッキングしていくことをやりきってほしいと思ってます。
とはいえ、スタートアップは理想と現実のギャップを埋めていく必要がありつつも、フェーズが次々と変わり新しいギャップが生まれてくるのでそもそも埋まらないとか、よく分からないボールが飛んでくることも多々ありますが。笑
溝口:
そういうギャップを埋める役割やプレッシャーみたいなものを、ZIGOROuさんは最前線で全部受け止めながら、冷静に物事を進めてくれていると感じてましたね。僕も今後同じように矢面に立つというわけではないですが、そういった部分も吸収できればと思います。
ちなみに、どうやって冷静さを保ち続けていたのかという部分はすごく気になります。笑
僕が見えている一部でも相当なプレッシャーだったと思いますが、僕が見えていないところでもきっと多くの課題を捌いていたのだろうと思うので。
ZIGOROu:
そういう意味で言えば、僕は冷静でも自信があるわけでもないんですよね。笑
でも、そうあるために理論武装をすることを重視してましたね。それに尽きる。無根拠な話はしないということは徹底していて、目的のために必要な論理展開とか統計的根拠とかを重要視してました。
逆にそういうものがあるからこそ、自信を持って話ができているわけで、過去の自分の実績なんてものはとっととアンラーニングするべきで、本当今が大事って感じですかね。だから本当に、なにかいつも勉強しているような気がします。パスタ作りとかね。笑
溝口:
なるほど。僕も過去のキャリアで執行役員は経験していますが、取締役という役割は初めてなので、ZIGOROuさんが言うようにアンラーニングして、過去の自分のやり方や実績にこだわらないようにしたいですね。
「今のベルフェイスに必要な取締役とは何なのか」をしっかり考えて、理論武装も含めて経営に貢献していかなければならないと強く思っています。ZIGOROuさんもそういった想いでバトンタッチしてくれていると思うので。
ZIGOROu:
ですね。あとは前から言っている通り経営や組織づくりは設計と変わらないと思っています。オペレーションの違いやドメイン知識はありますけど、適切な抽象度で理解していけば俯瞰してみれるし、それぞれに説明がつくんですよね。
どうしても一個一個の領域を担当をしている人っていうのは、そこの部分に集中しているので解像度は高いが視野が狭まってしまう。俯瞰して、今は正しい方向性に向かっているんだと言える人ってすごく重要だと思うので、そこは自分の役割だと思って冷静にやってきましたし、今後の溝口さんにも期待しています!
ー お二人ともありがとうございました!
最後に ”代表取締役 中島からのメッセージ”
ZIGOROuさんへ
プロダクトドリブンな体制になったのは、間違いなくZIGOROuさんが2年間をかけて組織・経営の在り方を変えてくれたからだと感じています。ビジネスサイドも強いベルフェイスではありますが、プロダクトの力で、しっかりと顧客へ価値を提供できるように成長しました。ZIGOROuさんには感謝しかないですし、これからもフェローとして支援し続けてほしいと思っています!
溝口さんへ
対談インタビューの中でも話が出ていましたが、ZIGOROuさんが抜けた後の組織を前に進められるのは、溝口さんしかいないと私も思っています。プロダクトの価値を最大限向上させるためには、組織が同じ方向を向いていることが必要不可欠です。溝口さんの圧倒的な推進力を持ってして、これからのベルフェイスを一緒に牽引していってください。これからもよろしくお願いします!
(写真:松田弘明)
プロダクトドリブン体制の構築から健全なガバナンス体制への移行 https://bs.bell-face.com/2023/02/01/2023020101/